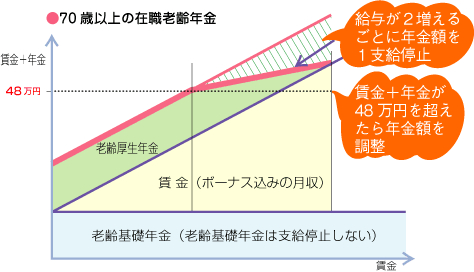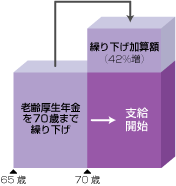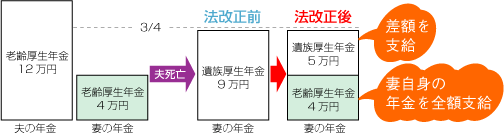| 離婚時の年金分割が可能に |
離婚時に、厚生年金の保険料納付記録を分割できる制度が導入されました。会社員の夫と専業主婦が熟年離婚するケースでは、従来は、妻が受け取れるのは自分の国民年金(基礎年金)のみで、厚生年金(報酬比例部分)はすべて夫に支給されるため、老後の年金額に大きな差がついていました。
平成19年4月以降に成立した離婚の場合は、当事者間の同意または裁判所の決定があれば、婚姻期間の保険料納付記録を分割することができます。
| P | O | I | N | T |
| ● | 平成19年4月1日以降に成立した離婚が対象。 |
| ● | 結婚してから離婚するまでの期間の厚生年金保険料納付記録を分割(独身期間は対象外)。 |
| ● | 分割できるのは50%まで。夫婦ともに厚生年金加入期間がある場合は、双方の合計の50%の範囲内で分割。 |
| ● | 年金分割を請求できるのは離婚後2年以内。 |
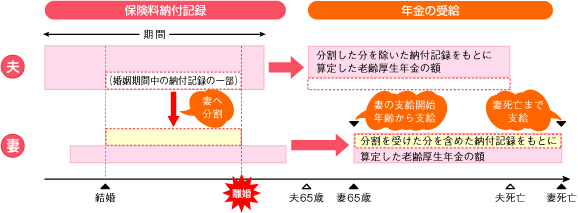
| 基金の対応 |